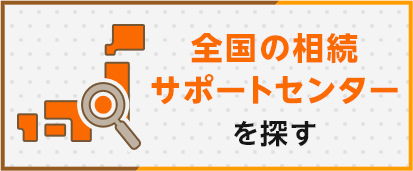お知らせ
NEWS
相続人としての資格を失う2ケースとは
2025.03.02
民法では法定相続人という規定を設け、亡くなった人の財産を誰が相続人として相続するかを決めていますが、その法定相続人が相続人たる資格を失うケースがあります。
稀ではあるものの、実際の現場では現実に相続人の資格を失うケースはおこっていますし、特定の相続人に財産を渡したくないという理由から、相続人の資格を失くす方法の相談などが生じています。
今回は相続人の資格を失うケース2パターンについて、留意事項も踏まえ具体的に見て行きましょう。
◆相続人の資格を失う2つのケース
ケース1【相続欠格】
相続人に不当・違法行為があった場合、当然に相続の資格を失う民法の制度
① 被相続人又は、先順位・同順位の相続人を殺害する行為に関わるもの
② 被相続人の遺言に不正な干渉を加えたり、遺言の偽造・変造・破棄・隠匿を行ったりするもの
欠格とは「人格の欠如」を指しますので、上記① ②の行為を行うことは当然に相続人たる資格を失うという規定です。
①は完全に犯罪になる為、稀ですが ②は自分の取分が少なく不利な内容の遺言を変造・隠匿などすることは現実にありうることです。
●留意)相続欠格となった者の子供は代襲相続人として相続財産を受け取る権利があります!
ケース2【相続人の廃除】
被相続人の手続きに基づき、家庭裁判所が審判で一定の相続人の相続権を剥奪する民法の制度です。
① 被相続人に対する虐待
② 被相続人に対する重大な侮辱
③ 相続人の著しい非行
この相続人を廃除することで、廃除された相続人は相続権を失うと共に遺留分も主張することが出来なくなるため、廃除される相続人にとっては重大な行為です。
その為、被相続人の意思だけではできず、家庭裁判所が排除を認める場合に限り排除が成立することになります。
虐待は解り易いですが、重大な侮辱の例として「80歳まで生きたんだから早く死ね!」と言われたことが判例で認められています。
【遺言で排除の意思表示をする方法】
生前に排除したい相手と対峙しながら裁判所に申し立てをすることで、更なる虐待を受ける可能性などがある場合、死後の遺言で特定の相続人に対して廃除の意思表示をすることができます。
実務的には被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行うことになりますが、裁判所で認められる理由や証拠を明確にしておくことがポイントです。
●注意)欠格同様に排除された者の子供には代襲相続権が生じます。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
相続権を合法的に失うケース2つを紹介しましたが、現実的には遺留分程度の財産を遺言で排除したい相続人に与えておく方法や、他の相続人があまり欲しがらない財産を遺言で指定しておくということが現実的な方法ではないかと思います。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
ちばPMA相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
ちばPMA相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載