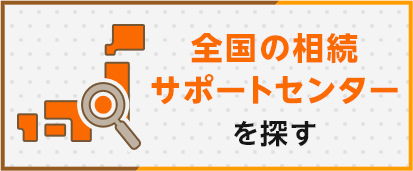お知らせ
NEWS
認知症対策に有効な5つの施策
2025.05.11
厚生労働省は2025年現在の認知症者数 471万6000人に対し、2040年には584万2000人に増加すると推計発表を行いました。なんと65歳以上の高齢者の15%(6.7人に1人が認知症)が認知症になるとのことです。
他人事ではない認知症問題、認知症になると全ての口座は凍結され、全ての法律行為が出来なくなります。今回はこの社会的問題である認知症に対して5つの対策を解りやすく発信します。
■5つの認知症対策とは
1. 家族信託
信託法の改正により、信託できる家族に自分の資産を信託契約に基づき信託することで、信託受託者は本人の健康状態に左右されずに本人に代わり財産の管理・運用・処分が出来る制度です。
家族信託は公正証書で組成する方法や、私文章で信託することもできますが、外部要因(銀行や親族)の関係上、可能な限り公正証書で交わすことをお勧めします。
2. 任意後見
任意後見制度は元気なうちに信頼できる後見人を自ら選択し任意後見契約を結ぶことで、任意後見人は財産管理や身上看護などを行うことができる制度です。
認知症になってから選任される法定後見人は家庭裁判所が後見人を決定する為、自ら希望する後見人(家族等)になる可能性が少なくなります。注意点は任意後見人には後見監督人が付くため、本人には必要がない不動産の売却や運用、相続対策などはできなのが特徴です。
3. 家族サポート証券口座
2025年2月からスタートした日本証券業協会が創設した「家族サポート証券口座」は、株式や投資信託を運用する証券口座が認知症等により凍結するケースに備え、家族代理人が本人に代わって口座の資産を売買換金できる新制度です。証券口座を保有の方は必見です。
4. 民間銀行の代理人指名制度
予め銀行に家族代理人の登録をしておくことで、本人に代わって家族代理人が預金の引き出しや振込が可能となる制度です。この制度は日常的な入出金に限定されることが特徴で、短期的な生活費対応や預金管理が目的となります。
5. 生前贈与
生前贈与は元気なうちに、親族や第三者に無償で財産を渡す法律行為です。事前に財産を受け取った家族等が、扶養義務に基づいて贈与金を使って療養身上看護をしてくれれば、実質的に資産凍結対策の機能に繋がることになります。
生前贈与には、様々な注意点(名義預金・定期贈与・非課税枠・相続時精算課税贈与・暦年贈与)がありますので、贈与の際は専門家に相談しながら行うようにしましょう。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
認知症対策として5つを紹介しましたが、実際の現場では、その家庭環境によって最善策は変わってきます。認知症になる前に、売買承継がいいのか、相続承継か? 信託か暦年贈与か相続時精算課税贈与かなどなど、親族事情や資産構成などの全体を俯瞰的に見て判断する必要があることを忘れないで下さい。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
ちばPMA相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
ちばPMA相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載